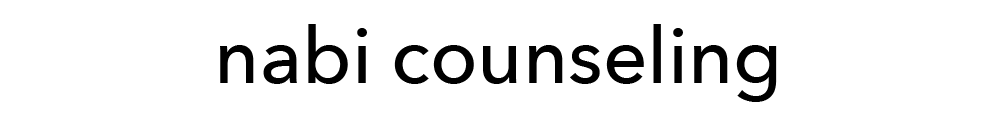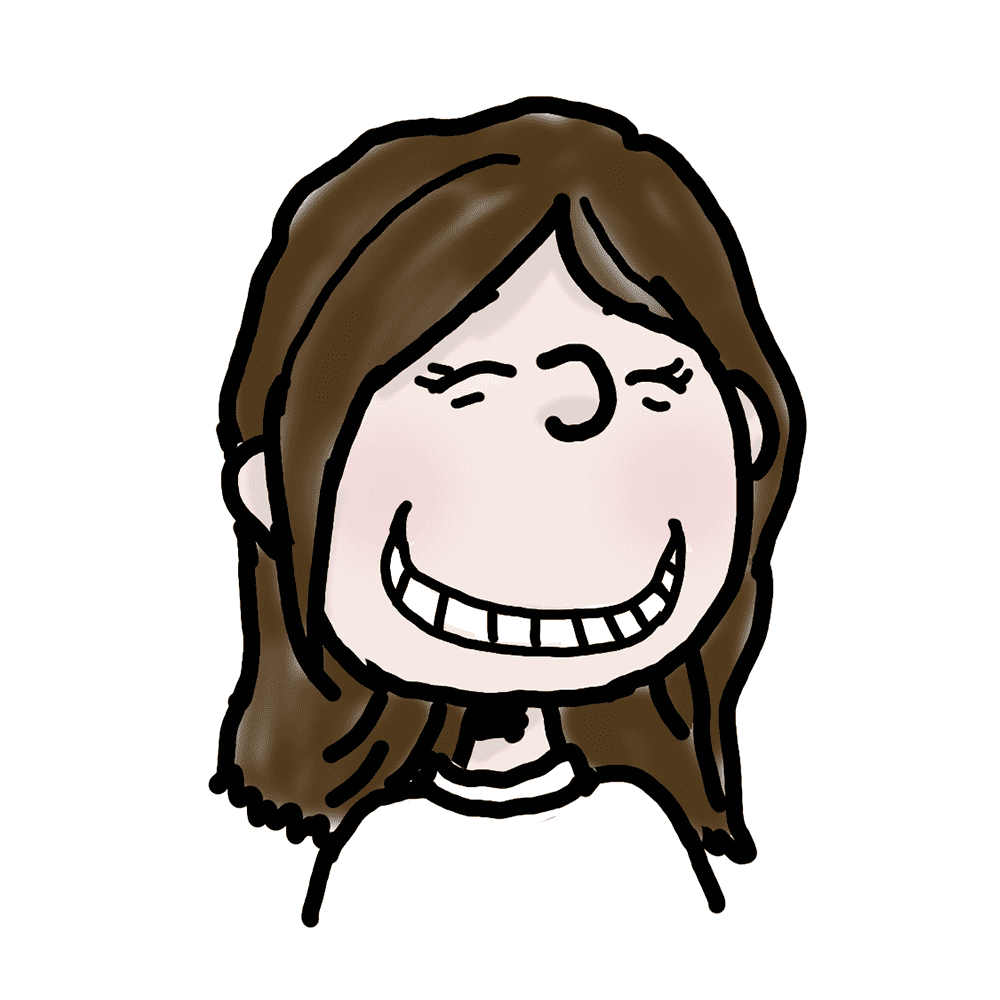前回の記事はこちらから

親が子供の死を経験すると、その次に生まれてくる兄弟の人生に影響を与えることがあります。
『The Ancestor Syndrome』(ご先祖さま症候群)によると、亡くなった子供(通常は幼い子供)が家族内で大きな悲しみや喪失を引き起こし、その悲しみを克服できていない親が、新たに迎える子供を「代替の子」と呼びます。
代替の子は、亡くなった子供に対する喪失感や悲しみが解消されないまま生まれてくるため、根底にあるのは未完了の悲しみです。
親が悲しみを十分に処理できていないので、感情的に「死んだ子供」に対して過度に執着してしまう。
そして、母親や父親は無意識のうちに、心の中で今生きている子供を「死んだ子供」として位置付けてしまい、今生きている子供との関係が不安定になってしまうのです。
代替の子は、無意識的に「死んだ子供を置き換える」役割を担わされ、亡くなった子供に対する親の理想や期待を無意識に受け取ってしまう。
そのため、生きることにプレッシャーを感じる場合があります。
そして、未完了の悲しみが根底にある代替の子に対し、家族内の喪失や困難を乗り越えるために迎えられる子供を、「修復の子」と呼びます。
親が過去の痛みを癒すためにその子供を迎えたとしても、悲しみや喪失を乗り越え、新たな子供を暖かく迎え入れることができる場合、その子供は修復の子です。
修復の子は、歓迎される存在として愛され、家族の中で新しい絆や希望を生み出す存在として扱われます。
この「代替の子」と「修復の子」から分かるように、その違いは、「親が子供が亡くなったことを悲しめているかどうか」です。
新しく生まれる子供が代替の子になってしまう場合、亡くなった子供に対する喪失感から、悲しみを直面することができず、家族内でその子の話をするのが、タブーとなってしまいます。
タブーとはつまり、ファミリーシークレットになることを意味します。
ファミリーシークレットになると、新しく生まれた子供は幼児的万能感から、「自分のせいで家族が暗い」と思い込み、生きることに罪悪感を感じてしまう。
さらに、亡くなった子供と新しく生まれる子供の間で「もつれ」が発生し、代替の子は文字通り、亡くなった子供の人生の代わりを生きることになってしまいます。
(もつれとは、家族内のメンバーの間で、無意識レベルで特別なつながりが発生すること。)
兄弟姉妹の一人が亡くなった子どもの苦しみや運命を無意識に背負おうとすることがあり、たとえば亡くなった子どもの代わりの人生を生きようとする者や、不幸や罪悪感を感じて自分を罰しようとする者が現れる場合があります。
棚田克彦氏著『トラウマは遺伝する
』p.166より
だけど、親がちゃんと向き合えなかったのは、新しく生まれた子供のようで、実は亡くなった子供の方なんです。
親が亡くなった子供の喪失を乗り越えた結果、歓迎され、愛される存在として扱われる修復の子から得られるヒントは、
亡くなった子供も家族の一員としての居場所が与えられれば、新しく生まれた子供も、現在の家族で居場所が与えられるということです。
たとえば、小さな観葉植物や写真など、亡くなった子どもを象徴する物を家の中に置くことで、家族の中で亡くなった子どもに敬意を払い、その存在を認めることが可能になります。
棚田克彦氏著『
(中略)
家族が亡くなった子どもに正しい居場所を与えたとき、家族システムに失われたつながりが回復します。兄弟姉妹たちは、生存者の罪悪感から解放されるだけでなく、亡くなった兄弟姉妹の存在を通じて内面的な強さや支えを得ることができます。トラウマは遺伝する
』p.175より
そう、誰かの人生の代わりなどではなく、自分の人生を生きられるようになる。
(つづく)
<参考>
続きはこちらから